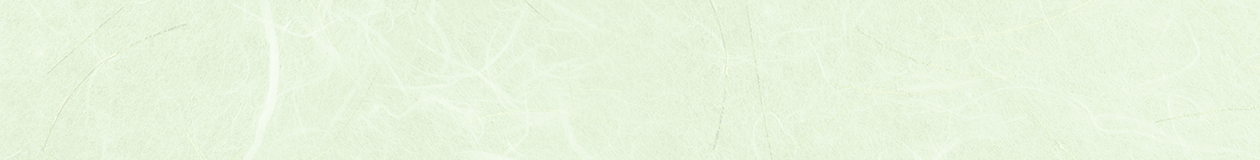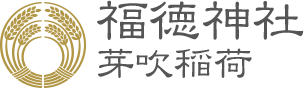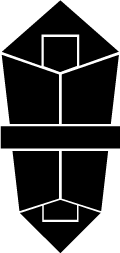令和7年 夏越の大祓を執り行いました

昨日、夏越の大祓を執り行いました。
その際、ご参拝者からお預かりいたしました夏越の大祓の祈願文浄書、そして人形は当日神前に供し、皆様の罪穢れが祓われますことをお祈り申し上げました。
大祓とは、一年十二ヶ月の折り返しである六月の末日に半年の罪穢れを祓い清める行事です。
平安時代の『延喜式』にも、六月と十二月の大祓が記されています。
大祓の行事の中に人形で身体を撫でて息を吹きかける行事があります。
これにより、人形に自分の罪穢を移し、お預かりした人形は海に流し、それぞれの罪穢は祓い清まるとされます。当社でも後日、流却神事を行い、お預かりした人形を海に流します。
一説にはこの夏越大祓は暑く疫病が流行る時期にそれを避け過ごす意味があったとされます。
また、『公事根源』には茅の輪をくぐるときに
「水無月の夏越の祓する人は千歳の命のぶといふなり」と唱えると記されています。
そして本年も神饌は
江戸時代の『料理調法集』の「年中嘉祝の飾」にある
「この日、瓢瓜の類、水菓子を銀器に入れて奉る。」との記述に倣いウリ科の野菜・果実をお供えしました。
また、氷の形をした外郎に魔よけの小豆を取り合せ、厄災を祓い、無病息災を祈る菓子として
夏越の祓の時期の風物詩とされている「水無月」をお供えし、ご参列の皆様にはこちらをお下がりとしてお頒ちしました。
本年は例年よりも早く厳しい暑さが続いております。
くれぐれもご自愛いただき、この酷暑を健やかにお過ごしになられますことを心からお祈り申し上げます。